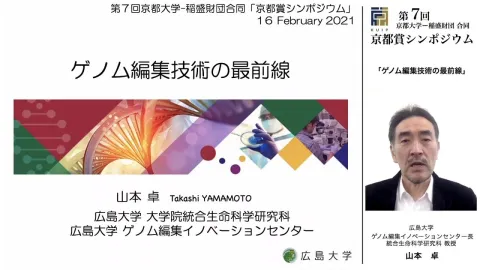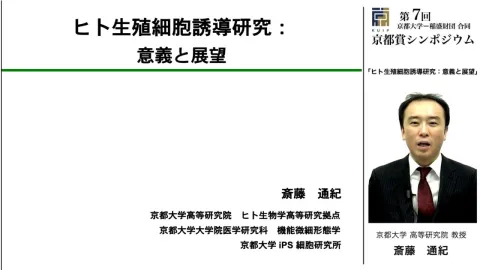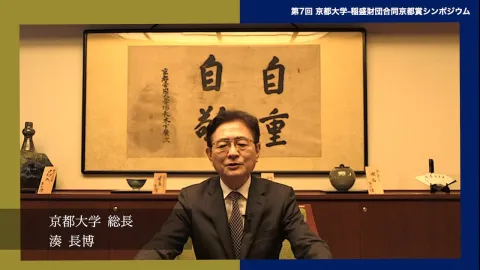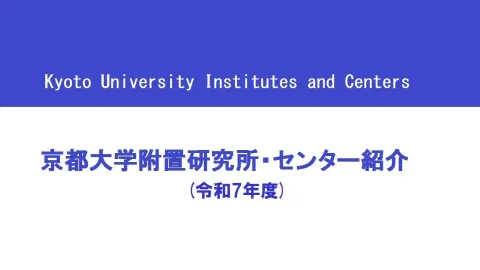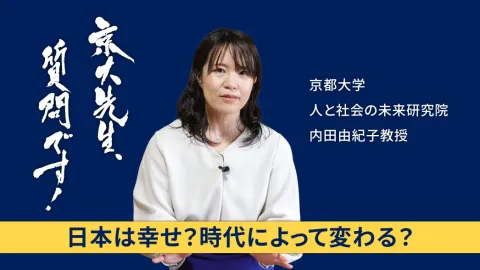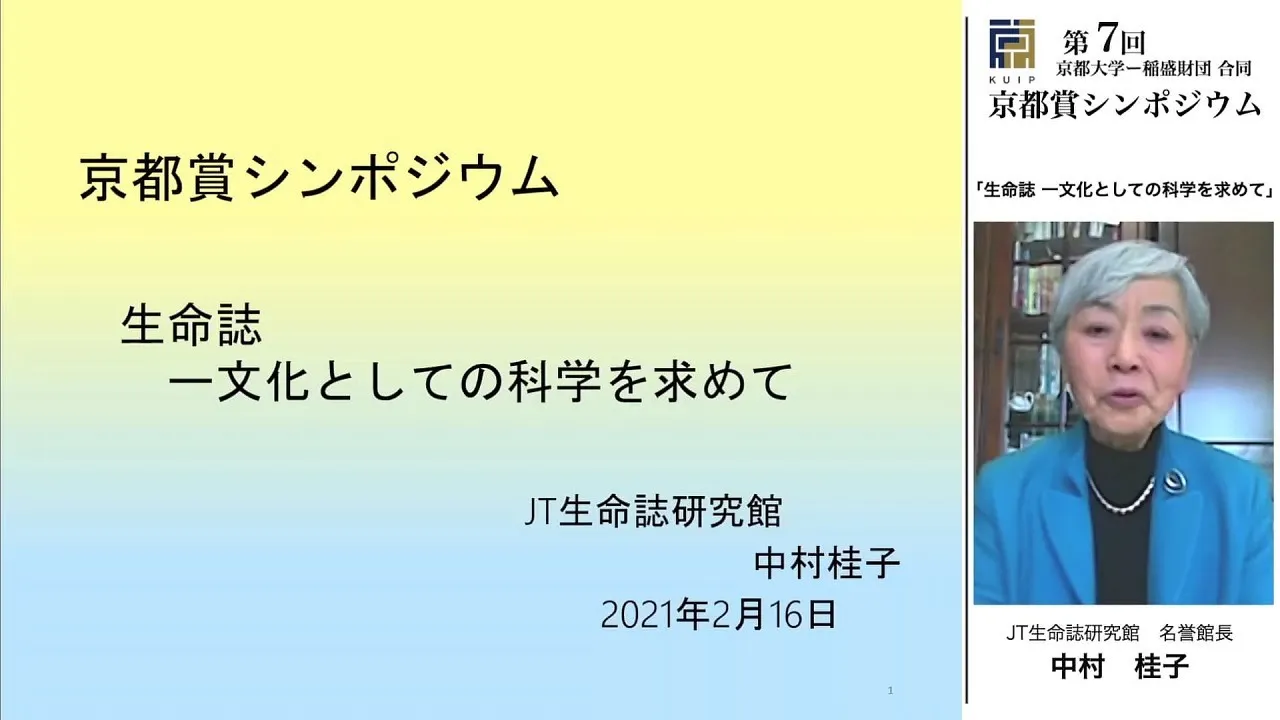
第7回 京都大学 − 稲盛財団合同京都賞シンポジウム「世界を動かした技術とその道しるべ -技術革新と生命倫理-」
「生命誌 - 文化としての科学を求めて」
中村 桂子(JT生命誌研究館 名誉館長)
生命とはなにか。少しくだいて言うなら生きているとはどういうことだろうという問いは誰もが抱くものだろう。それは、人間とはなにか、心はどこにあるのか、死とはなにかなどに広がり、生きる意味を問うことにつながる。
従来この問いへの答は、哲学や宗教に求められてきたが、近年、生命科学が考察の基盤を提供できるようになった。
この時の生命科学は、生命体を機械と捉えその構造と機能の解析に止まることは許されない。生きものの特徴に注目し、その全体を理解することが不可欠である。
幸い、20世紀も終盤に入り、細胞内に存在する全DNAをゲノムとして捉えることで、従来の生命科学の方法を生かしながら全体、歴史、関係、階層、多様、普遍など生きものの特徴を知ることができるようになった。そこで生きものを生きものとして理解する知として生命誌(Biohistory)を提唱し、それを研究館(Research Hall)という場で実践している。ここで忘れてはならないのは、ゲノムで生きもののすべてがわかるものではないということである。
地球上に存在する多様な生物は40億年近く前に生れた細胞を共通祖先とし、全生物のゲノムには生命の歴史と関係が書き込まれている。それを知ることにより、現代科学を支える機械論的世界観から生命論的世界観への転換が起きてくる。人間も生物の一つであり、40億年近い歴史を踏まえた生き方を考える必要がある。
私たちの日常体験から生れるのは、生命論的世界観であり、学問と日常、つまり科学による知識と体験とは一体でなければならない。これを哲学者大森荘蔵は「重ね描き」と呼んだ。一人の人間の中で研究者と生活者が乖離することなく存在する状況である。
こうして科学が文化として社会の中に根づき、生きものを基本にした暮らしやすい社会づくりへの道が拓けるのである。「重ね描き」を具体的な事例でお話し、21世紀の生き方を御一緒に考えたい。
#京都賞シンポジウム #中村桂子 #生命誌 #JT生命誌研究館
--------------------------------------------------------------------------
京都大学-稲盛財団合同京都賞シンポジウム(略称“KUIP”クイップ)は、京都大学主催・公益財団法人稲盛財団共催により、2014年から毎年開催している国際シンポジウムです。2020年度は初めてオンラインで開催いたしました。
京都大学-稲盛財団合同京都賞シンポジウム
http://kuip.hq.kyoto-u.ac.jp/ja/
過去の講演
http://kuip.hq.kyoto-u.ac.jp/ja/archives/video
京都賞
https://www.kyotoprize.org/
※所属・役職・内容は動画制作当時のものです。
- 部局
- 分野
- タグ