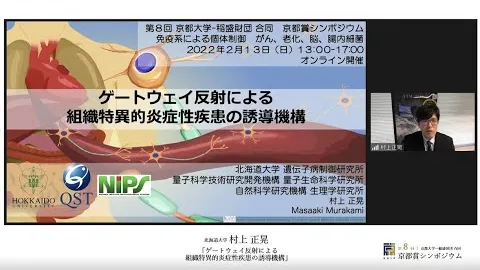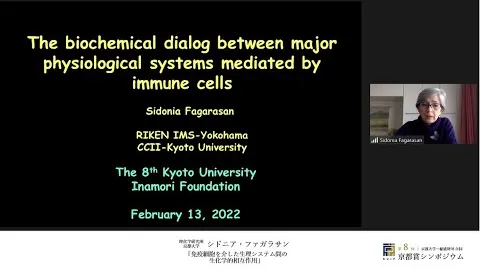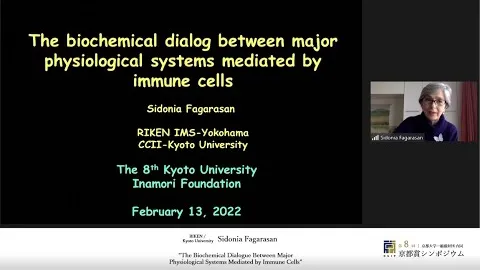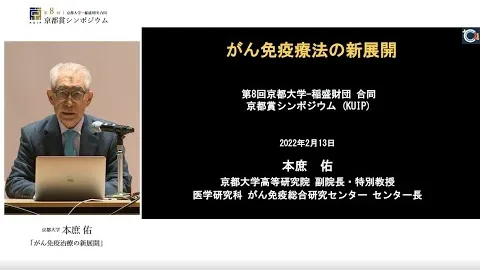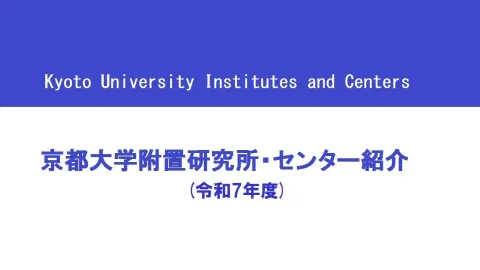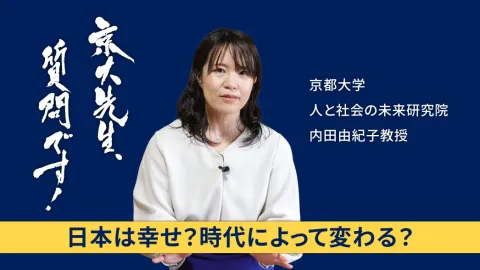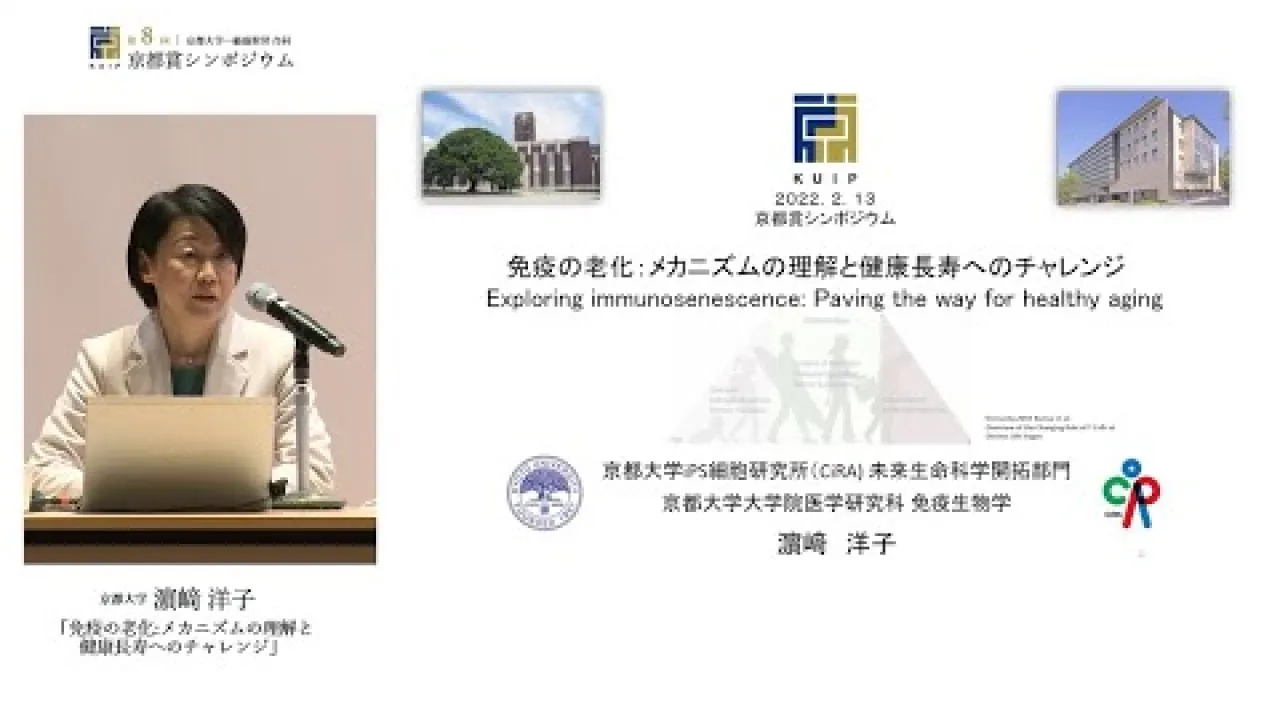
≪0:45:47≫
第8回 京都大学 − 稲盛財団合同京都賞シンポジウム 「免疫系による個体統御ーがん、老化、脳、腸内細菌」
「免疫の老化:メカニズムの理解と健康長寿へのチャレンジ」
濵﨑 洋子(京都大学 iPS細胞研究所 教授)
歳をとるにつれて病原体やがんを排除する正常な免疫機能が低下し、感染が重篤化しやすくなり、がんの発症率も上昇する。他方、同じ免疫応答でも炎症反応や自己免疫のリスクは増大し、様々な加齢関連疾患の発症につながるとされる。このように、一見相反する二面性を持つ「免疫老化」という現象は、年齢とともに増加する様々な疾患に共通した基盤要因となるが、その実態と原因については不明な点が多い。
T細胞は、抗体を産生するB細胞や食細胞の機能を調節すると共に、がん細胞やウイルス感染細胞を直接殺傷するなど、獲得免疫応答の主役となる免疫細胞である。それにもかかわらず、T細胞の産生臓器である胸腺は、幼少期をピークに徐々に脂肪におおわれながら小さくなり(胸腺退縮)、新たに産生されるT細胞数は20歳代ですでに新生児期の約1/10以下に低下する。このためT細胞は体内で長く維持される必要があり、免疫担当細胞の中で最も大きく加齢の影響を受けるとされる。
私たちは、この胸腺の発生と退縮の仕組み、そしてT細胞の産生が生涯の比較的早い時期に低下することが、加齢とともに増加する様々な病気とどのようにつながるのかを理解し、その予防と介入方法を開発すべく研究を行っている。また、発生過程の時間軸がほとんどの人でほぼそろうのに対して、老化の過程や程度には極めて大きな個人差がある。なぜ、この差が生じるのか明らかにすることも重要である。本講演では、最近行った20歳代若齢者と70歳代高齢者の新型コロナウイルス反応性T細胞を比較した研究なども紹介しながら、これらの点について議論したい。
今後寿命はさらに延び、現在20歳代の若者は平均100歳以上生きるとの試算もある。つまり私たちは今後、胸腺が退縮した後より長くT細胞をよい状態で維持していく必要がある。この先人口が一層増加していく高齢者の免疫の特性を理解し、年齢にあった適切な医療を提供することは、健康長寿社会を実現するため現代医学に課せられた喫緊の課題である。
#京都賞シンポジウム #濵﨑洋子 #免疫の老化 #京都大学
--------------------------------------------------------------------------
京都大学-稲盛財団合同京都賞シンポジウム(略称“KUIP”クイップ)は、京都大学主催・公益財団法人稲盛財団共催により、2014年から毎年開催している国際シンポジウムです。昨年に続き2021年度もオンラインで開催しました。
京都大学-稲盛財団合同京都賞シンポジウム
http://kuip.hq.kyoto-u.ac.jp/ja/
過去の講演
http://kuip.hq.kyoto-u.ac.jp/ja/archives
京都賞
https://www.kyotoprize.org/
※所属・役職・内容は動画制作当時のものです。